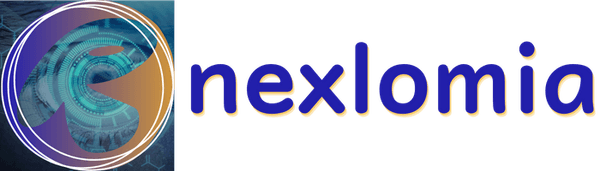こんばんは。のりーです。
昔むかし、人々は物語を囲炉裏端で語り継ぐことで、大切な知恵を次の世代へと伝えてきました。やがてグーテンベルクが活版印刷を発明し、書物が生まれると、「知」は爆発的に、そして正確に世界へと広がっていきました。
歴史は繰り返す、と言います。
そして今、AIという新しい「情報の革命」が、私たちの働き方、そして「言葉」そのものの価値を、根底から問い直そうとしています。
新しい技術は、いつだって少しミステリアスで、ちょっぴり怖いもの。
例えば、デザインツールのFigma。先日、「テキストで指示するだけでAIがデザイン案を作り、ボタン一つでWebサイトとして公開までできる」という、まるで魔法のような新機能を発表しました。
急速な技術革新を実感したとき、私達の胸には不安がよぎります。
でも、私は思うんです。こうした変化の時こそ、私たちは「人間にとっての本当の価値とは何か」と、真正面から向き合うことを迫られる。それは、自分自身の在り方を見つめ直す、最高のチャンスでもあるのだと。

📝現場の「小さな事件」が教えてくれたこと
具体的な事例として、最近私の職場である、IT系企業の現場で立て続けに起きた、2つの小さな「事件」についてお話しさせてください。
一つは、修正を重ねるうちに、デザインがいつの間にか古いバージョンに戻ってしまう「先祖返り」事件。「どうすれば防げますか?」とコーダーに尋ねても、返ってくるのは「気をつけます」という言葉。
では、チェック体制を強化しますか?人の注意力に頼る仕組みは、スピードを落とし、手間と時間を増やし、結果的にコスト増につながる…その限界に、私たちは気づいていました。
もう一つは「1ヶ月半待ち」事件。これは、専門家から専門家へと仕事が受け渡される、現在の「分業制」が生んだ弊害でした。特定のスキルを持つ人がボトルネックになると、プロジェクト全体が止まってしまうのです。
この2つの事件の根っこは同じです。それは、人と人の間にある、情報の伝達ロス。まるで、不正確な伝言ゲームのように、大切な情報が劣化したり、滞ったりすることで生まれる、すれ違いです。
道具が壊す「壁」と、生まれる「越境」
Figmaのようなツールは、このカッチリと分かれた「分業制の壁」を溶かし、デザイナーやディレクターが、ある程度コーディングの領域まで「越境」することを可能にしてくれます。
専門家同士の受け渡しが減れば、時間のロスも手間も劇的に減る。働き方そのものが変わっていくはずです。
そして何より、デザイナーの頭の中にある完成イメージが、劣化することなく形になる。情報伝達のロスが、限りなくゼロに近づきます。
これまで価値があった「指示通りに作業を実行する力」は、ツールが肩代わりしてくれるようになります。すると、価値は別の場所へと「移動」せざるを得ません。
では、その移動する価値とは、一体何なのでしょうか?
活版印刷が変えたもの、AIが変えるもの
ここで、少し歴史に目を向けてみましょう。
活版印刷が登場する前、価値は「聖書を記憶し、語れること」にありました。情報そのものが希少だったからです。
しかし、誰もが聖書を手にできる時代になると、「ただ知っている」ことの価値は薄れ、「その教えをどう解釈し、何を語るか」という、個人の思想や言語化の力が問われるようになりました。
今、AIが起こしているのは、これと同じ構造変化です。
AIは、いわば「アイデアの活版印刷技術」。これまで専門家の頭の中にしかなかった完成イメージを、誰もが安価に、大量に、正確に具現化できるようになります。
このとき、価値を持つのは何か。
それは、「そもそも、何を創りたいのか」という、意志を「言語化」する力です。
自分が何をしたいのか、するべきなのか。
この漠然とした想いを、AIにも、そしてチームの仲間にも伝わる、明確で力強い「言葉」にできるか。
言葉にできない想いは、AIに伝えることすらできません。
人は言葉があるからこそ、過去から学び、未来を構想できるのですから。
活版印刷が「何を言うか」の価値を高めたように、AIは「何を創りたいか」という意志の言語化の価値を、飛躍的に高めていくでしょう。
そして、その言語化された構想を、多様な人々の心に響くように伝え、プロジェクトを成功に導く「翻訳」の力も、同時に重要性を増していきます。
技術は、私たちの仕事を奪うのではありません。
「あなたは何を望み、何を言葉にするのか?」と、私たちの人間性そのものを、問いかけているのです。
💪リデザインのためのアクション
- 最近「伝言ゲーム」で困ったことを思い出してみよう: 「言った」「言わない」のすれ違いは、なぜ起きたのでしょう?その原因を探ることが、改善の第一歩です。
- あなたの「こうなったらいいな」を言葉にしてみよう: 仕事でも、暮らしでも構いません。漠然とした願いを、誰かに語れるくらい具体的な言葉にしてみる練習です。
- 誰かの「漠然とした想い」を言語化する手伝いをしてみよう: 「それって、つまりこういうことですか?」と問いかけ、相手の頭の中を整理してあげる。それは最高の「翻訳」の実践です。
🎯次回予告
来週のnextlomiaのテーマは【今月のリデザイン】。
45歳で大手航空会社を早期退職し、農家を目指して小豆島へ。しかし、彼を待っていたのは、移住前には見えていなかった甘くない現実だった。
地縁も血縁もない土地で、人の縁だけを頼りにたどり着いた、熊本・天草。さあ、これからという矢先に、あの熊本地震が襲う――。
波乱万丈のキャリアリデザイン、その物語をお届けします。お楽しみに。
Newsletterを受信する
WEB公開の1ヶ月前にメールでお送りします📧 いつでも登録を解除できます。