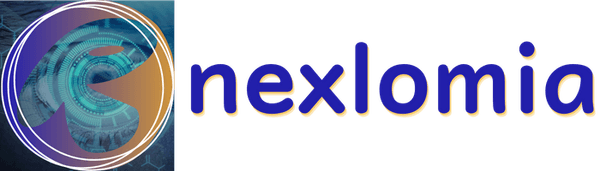小豆島にあるエンジェルロード。干潮時には水面下の道が現れる
東京から小豆島への脱サラ移住で体験した農家の現実。人口減少、インフラ不足、野生動物との闘いなど、理想と現実のギャップから見える地方移住の課題と可能性を探ります。移住検討者必見の体験談。のりーです。3月に入り、だいぶ寒さが緩んできましたね。
一方、花粉が飛び始め、私も毎年この時期はくしゃみや目のかゆみと格闘しています。皆さんは大丈夫でしょうか?ニュースレターの移行先を探していたら、いいものを見つけました。ただ、少し準備が必要なので、移行先のサービスでの配信は4月からにしました。
さて、今週は「変化と移行」をテーマに、大手航空会社から脱サラ・地方移住して農家に転身した、夫・筒井洋充のストーリーをお届けします。 最後にお知らせがあります。暮らしと働くをリデザインするというテーマに関心のある方は、お見逃しなく!✨️今月のリデザイン:理想の暮らしと現実のギャップ
45歳という比較的若い年齢で早期退職制度を利用し、長年勤めた航空会社を円満退職した私は、期待に胸を膨らませて小豆島での新生活をスタートさせた。
東京の喧騒から離れ、自然に囲まれた穏やかな生活。自分のペースで農業に取り組み、地域の人々と交流する。そんな理想の田舎暮らしを思い描いていた。
しかし、実際の田舎暮らしはバラ色ではなかった。予想もしなかった課題の連続。今回は、最初の移住先だった小豆島での体験を中心に、理想と現実のギャップについて掘り下げていく。
小豆島での農業生活――理想と現実
小豆島での農業生活は、ある意味で理想的な側面もあった。日の出とともに起き、日の入りとともに仕事を終える。体を動かし、汗をかく。
これは動物として本来の働き方なのかもしれない。満員電車に揺られることも、夜遅くまでの残業もない。自然とともに一日が始まり、終わる。
この生活リズムの変化は、予想外の効果をもたらした。わずか2年で体重が10kg減り、20代の頃の体型に戻ったのだ。無理なダイエットをしたわけではない。
規則正しい生活、三食きちんと食べること、適度な運動が自然と身についただけである。運動そのものよりも、生活リズムを整えることの方がダイエットには効くのではないかと思うほどだ。
しかし、田舎暮らしは牧歌的ないいことばかりではない。特にオリーブ栽培を始めてすぐに直面したのは、野生動物との闘いだった。
小豆島のオリーブ農業と野生動物との闘い
小豆島は古くからイノシシと戦ってきた島で、「シシ垣」という遺跡が今も残っている。万里の長城のように、山の尾根に沿って築かれた石垣が島のあちこちに見られるほどだ。一時期、豚コレラの影響でイノシシは島から姿を消したという。
しかし、彼らは泳いで海を渡るため、いつの間にか再び島に戻ってきた。
さらに厄介なのは鹿だ。鹿はオリーブにとって、イノシシよりはるかに天敵である。葉を食べるだけでなく、木の皮まで剥いでしまう。高尾農園の多くのオリーブの木は、地上1メートル20センチほどまでの葉が完全に食べられていた。
植えたばかりのオリーブの苗木が一晩で食べられてしまうこともあった。鉄の柵や電気柵を設置しても、彼らはすぐに弱点を見つけて侵入してくる。まさにイタチごっこだった。
この問題は人口減少とも関係している。かつては猟師が多く、有害鳥獣の駆除も活発に行われていた。しかし、高齢化と人口減少に伴い、猟師の数も減少。野生動物の数は増加の一途をたどっている。
農業を守るための対策費用は年々増加し、その負担は小規模農家にとって大きな重荷となっている。
小豆島の秋祭り――地域の結束と過疎化の現実
小豆島での生活で最も印象に残っているのは、秋祭りだ。「太鼓まつり」と呼ばれるこの祭りでは、1〜2トンもある太鼓台を地域の人々が担いで練り歩く。
各地区がそれぞれ太鼓台を持ち、競い合うように神社に奉納する様子は壮観だった。地域の一体感を肌で感じられる瞬間だ。
東京で育った私にとって、地域のまつりといえば盆踊りくらいしか経験がなく、この祭りの迫力と熱気は新鮮な体験だった。
しかし、この伝統行事も人口減少の波に晒されている。1〜2トンもある太鼓台を担ぐには、相当数の若い力が必要だ。
祭りの参加者の高齢化が進み、一部の地区では太鼓台の奉納を断念するところも出てきていた。担ぎ手の数が足りずに、地域間で人を相互に融通する取り組みも始まったと聞いている。
太鼓台に乗る子ども「乗り子」は、かつては男の子が務めていた。しかし子どもの減少により、今では女の子も担うように。性別の壁を越えてでも伝統を守ろうとする姿勢に、地域の強い意志を感じた。
「この祭りがなくなったら、地域の結束も失われてしまう」と地元の方は嘆いていた。何百年も続いてきた伝統が、わずか数年で途絶える可能性がある。これもまた、過疎化がもたらす見えない喪失の一つだった。
小豆島の交通事情と人口減少の兆し

島にはごま油のカドヤの工場がある。小豆島そうめんはごま油が塗ってある。コシがありそうめんの常識が変わった
小豆島はコンパクトな島で、面積は約150平方キロメートル。私たちが住んでいた当時の人口は約3万人だった。
島内には複数の港があり、小豆島と高松を30分ほどでつなぐ高速船もあった。岡山と高松行きの船が1時間に1便はあり、離島としては交通の便はよい方だったと思う。
しかし、どこに行くにも船が必要なのは大きなデメリットでもある。天候が悪いと欠航することもあるし、最終便に乗り遅れれば島に帰れない。また、物流コストも高くなる。
私たちが小豆島に住んでいたのはわずか2年ほどだったが、その数年後、経営難から船の航路が一つ廃止されたと聞いた。
さらに深刻だったのは、島内の企業が人手不足による倒産の危機に瀕していたことだ。小豆島は醤油やそうめんなどの食品製造業が盛んだが、若者の流出により働き手が不足。労働者を雇用しても定着率が低く、企業の存続が危ぶまれていた。
働く場がなくなれば生活できなくなるため、人口減少はさらに加速する。便利だった船の便も減り、インフラも縮小していく。この負のスパイラルは、移住を決めた当初は想像していなかった現実だった。
誰も教えてくれなかった過疎化の現実
小豆島で最も衝撃を受けたのは、過疎化のスピードだった。統計は知っていたが、目の前で起きる変化の速さは想像を超えていた。
高校卒業後に島を出る若者たち、30%を超える高齢化率、増え続ける空き家。これらを目の当たりにし、10年後、20年後の小豆島を想像せざるを得なかった。
船の便は減り、商店は閉まり、医療機関も縮小していく—この将来像に、長期的な生活設計の見直しを迫られた。
過疎化は単なる数字ではない。祭りの担い手不足、野生動物管理の困難さ、交通インフラの脆弱性として日常生活に現れる。
一度始まった人口減少は加速度的に進行し、地域社会の基盤を揺るがしていく。小豆島での2年間は、田舎暮らしの魅力と同時に、日本の地方が抱える構造的課題を身をもって体験する期間となった。
理想と現実のギャップを知り、より現実的な視点で地方生活を考えるようになった。
次の「今月のリデザイン」は、小豆島から天草へ再移住することになった経緯について話したい。なぜ一度移住した地を離れ、新たな土地を選んだのか。その決断の裏にある思いや、二度目の移住で気づいたことなど、地方移住を考える方々の参考になる体験を共有する予定だ。
💪リデザインのためのアクション
1️⃣日常に小さな変化を取り入れる
- 通勤・通学ルートを少し変えてみる・週に一度、いつもと違う場所で食事や作業をする・朝の時間を15分早く起きて、自分だけの時間を作る
2️⃣身近な地域を再発見する
- 自宅から徒歩30分圏内の未訪問スポットを週末に探索する・地元の季節イベントに参加してみる・地域の特産品や旬の食材を意識的に取り入れる
3️⃣生活空間に変化をつける
- 部屋の家具配置を少し変えてみる・季節に合わせた小物を取り入れる・植物や花を飾り、自然を室内に取り入れる身近なところから、自分のペースで始めてみませんか?
🎯次回予告
次週は、九州NOWです。地方銀行の大学発ベンチャー支援の取り組みについてお届けします。
これまでの回でお伝えした、熊本大学の半導体学部や附属小中学校の国際クラス。大学構内を歩いていたとき、「あれ?」と目を引いたのは地方銀行のロゴがついた建物でした。
なぜ銀行の拠点が大学内に?興味を持って調べてみると、全国的にもめずらしい大学発ベンチャー支援の取り組みが見えてきました。地方銀行が大学発ベンチャーを支援することに、どんな意味があるのか?
お楽しみに!